森里山海につながる酒を求めて「カクウチBar農!」@青山ファーマーズマーケットを体験

米づくりから醸造まで一貫して酒造りを行う22の酒蔵によって結成された「農!と言える酒蔵の会」。今年は、青山ファーマーズマーケットにて日本酒ポップアップバーを開催。フードライターとして日本各地の酒蔵を取材し、日本酒をこよなく愛する松浦裕香里氏が体験した。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
土とつながる日本酒づくりを持続可能にする“未来へのバトン”

かつては日常の食卓や風景に当たり前のように並んでいた、日本酒。人生の節目を迎える祝い事やイベントでも酒が振る舞われ、時には何気ない日常の疲れを癒すツールとしても愛されてきた。そんな日本人のハレとケに深く根ざした日本酒だが、昨今では消費量も減り続け、日本酒文化を取り巻くサステナビリティに危機が迫っている。
米づくりから醸造まで一貫して酒造りを行う22の酒蔵によって結成された「農!と言える酒蔵の会」。「サステナビリティ」という言葉が生まれる前から取り組まれてきた米、酒づくりをとおし地域の文化、土壌、自然と人とのつながりを消費者へ届けることを目的としている。2019年の会発足以来、さまざまな活動を行ってきたこの22蔵が伝えていきたい、これからの酒のあり方とは。一杯のグラスに注がれる酒に込められた、蔵人の想いと技、米、麹、水から広がる日本の農業、風土の“未来へのバトン”について考えていく。
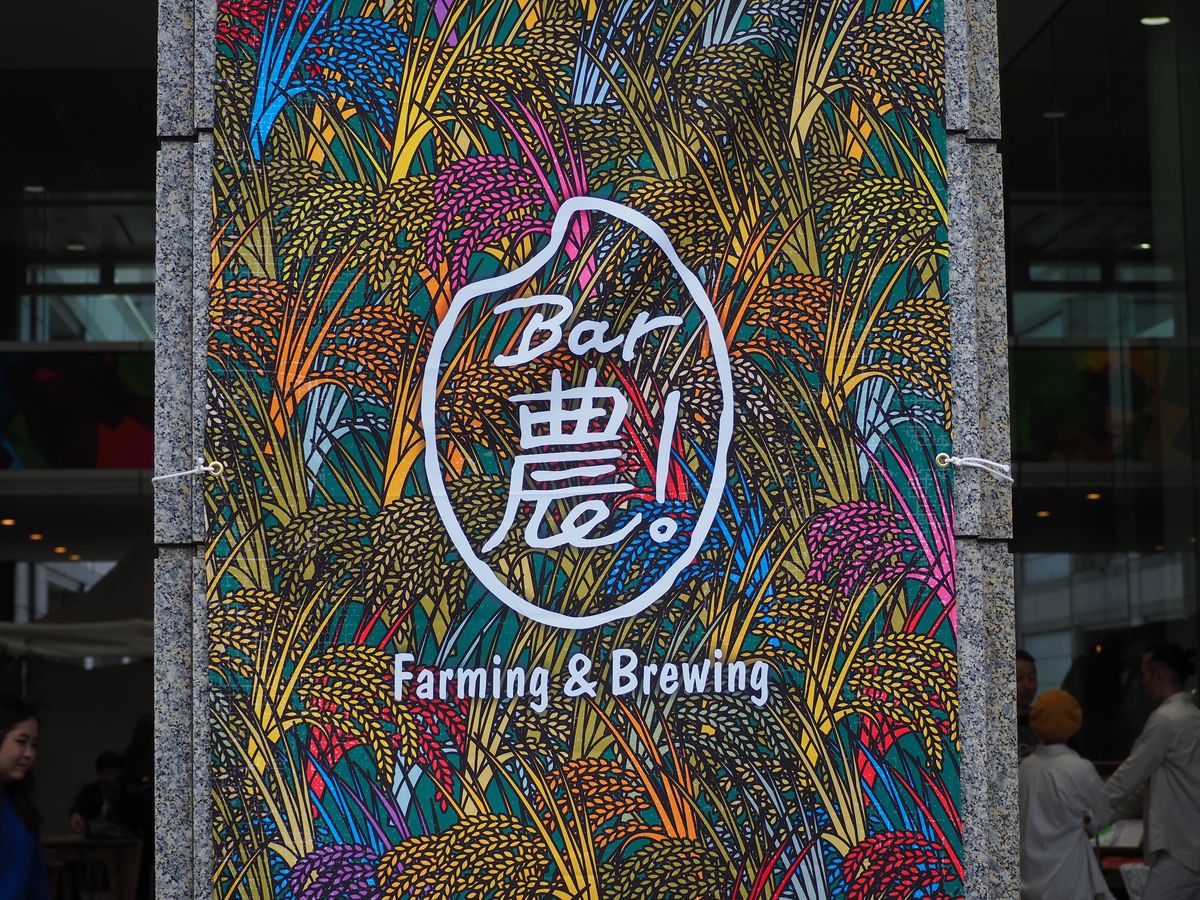
10月7・8日、11月25・26日の計4日間にわたり、青山ファーマーズマーケット内において開催されている角打ちイベント「カクウチBar農!」。米づくりから酒づくりまでを一貫して行う酒蔵の集まり「農!と言える酒蔵の会」によるカクウチイベントだ。全国に1400以上あるといわれる酒蔵。多様な酒づくりとの向き合い方がある中で、同会の蔵元たちはどのような意図や想いを持って酒づくりを行なっているのか。イベント2日目、10月8日に参加していた酒蔵のブースを巡りながら、蔵元たちと共有した時間を振り返る。
まずは、気になる1杯を片手に。カラダを温めてから。

1枚100円のチケットを購入し、酒と交換。一杯60mlからの計り売り。銘柄によって必要チケット枚数が異なり3枚〜18枚までさまざま。
週末になると多くの人で賑わう青山ファーマーズマーケット。多くの生産者が新鮮な農産物を持ち寄るこの都会のマーケット。野菜や加工品が並ぶ中、日本酒の蔵人と会えるイベントはめずらしい機会だ。ピロティと呼ばれる会場内の屋根付きのエリアで「カクウチBar農!」は開催されている。肌寒さを感じるこの季節、雨風を気にせずに楽しめる会場なのが嬉しい。

チケットを購入したら会場奥のキッチンカーで酒を選び注いでもらう。マイカップを持参することで、チケット1枚分(100円分)が値引きになるので、積極的にマイカップやマイグラスを持参して参加したい。
今回のイベントには日替わりで5〜6蔵が会場に出店。日頃なかなか会うことができない蔵人が自ら接客をしてくれる。会場ではゆったりとした空間の中、宴会を開いている人や、蔵人とのコミュニケーションを楽しむ人とさまざまで、穏やかな雰囲気が印象的だった。というのも、よくある日本酒イベントでは規模によっては、ゆっくり蔵人と話をしながら酒を飲み、選び、買うということが難しいほど混雑していることも少なくない。この少々贅沢な雰囲気が、今回のイベントテーマ「触れる・体験する」につながっており、酒蔵にとっても参加者にとっても魅力的なのだろうと感じた。

キッチンカーでは、日本酒を飲む時に欠かせない「和らぎ水(チェイサー)」も無料で提供。マイカップと合わせてぜひマイボトルも持参すれば、酒の合間の一息をつきながら、酔いの速度も緩やかになり安心だ。こまめに水分をとって、楽しくイベントに参加したい。

ファーマーズマーケットではキッチンカーも多数出店している。ファーマーズマーケットグルメと一緒に日本酒ペアリングをしてみるのもこのイベントならではの楽しみ方だ。
逆境から生まれた純米酒。無農薬栽培の「山田錦」を味わう酒|森喜酒造場

「森喜酒造場」5代目の森喜るみ子氏。苦悩の時期の境遇を重ねた、漫画「夏子の酒」と出合い、作者・尾瀬あきら氏に手紙を書いたことがきっかけで紹介された蔵元から純米酒づくりを学ぶ。代表銘柄「るみ子の酒」は彼女が醸した最初の純米酒として、いまも多くの日本酒ファンから愛されている。
ブースの前でイキイキと笑顔で話をする姿が印象的だったのが、三重県・伊賀市にある森喜酒造場の森喜るみ子氏。いまでこそ多く見かけるようになった女性杜氏の草分け的存在である彼女は、蔵の跡取り娘として多くの困難を乗り越えてきた。
蔵を継いだものの、大手酒造メーカーの下請けから契約を打ち切りにされ、廃業という言葉が過ぎる毎日だったという。そんな中必死の想いで純米酒の勉強をし、杜氏としての技を得た。以後、醸造アルコールを添加しない米、麹、水だけで醸す伝統的なつくりを貫く全量純米酒蔵となった。
今回のイベントで振る舞われている「英(はなぶさ)」は、蔵元が育てた無農薬栽培の山田錦を使った自慢の銘柄だ。蔵周辺の圃場整備(農地の区画整理、農道、農業用用排水路の整備)を機に始めた自社田での酒米栽培。現在は酒米の原生種「山田錦」を自社および契約農家で無農薬栽培している。肥料には酒粕のみを使用し、余計な手入れをしないことで、稲そのものが持っているポテンシャルを発揮できるように栽培している。蔵の年間製造石数はわずか300石(540ℓ)。
米づくりから酒づくりまで丹念に、少量生産だからこそ可能な手の込んだ酒づくりを行なっている。るみ子氏の人柄に触れながら、山田錦の力強くも穏やかな香りと旨みを堪能させてもらった。
4世代の哲学と意志を継ぎ、自然環境に寄り添い醸す酒|仁井田本家

精米度合いは88%と玄米の限界に挑戦。いい米だからこそ、削りすぎることなく味わいを最大限に活かした。酒を絞った後、仕込みで使った木桶に再度戻し、熟成させた酒は複雑みを帯び奥行きのある独特な味わいを放つ。
続いてお話を伺ったのは、福島県郡山市の仁井田本家。アウトドアブランドなどとのコラボレーションも行なっており、日本酒に親しみがない人でも、一度は名前を聞いたことがあるという人もいるのではないだろうか。
「田んぼと水を守り、酒と人を育てる」蔵として、これまでも農薬や化学肥料を使わない「自然米」を原料に、土地の水、蔵付きの酵母を使った自然派の酒づくりを行なってきた。そんな仁井田本家が今回のイベントで提供する銘柄は「にいだぐらんくりゅ」。十八代目蔵元で杜氏の仁井田穏彦氏が「仁井田の最高峰」と自信を持って言い切る、仁井田本家の歴史と哲学が詰まった1本だ。
十六代目が80年前に植えた自社山の杉を使った木桶を使い、十七代目が考案した自然派の酒づくりの技術をもとに、十八代目で現蔵元が栽培した自社田の米を原料にし、十九代目候補が森をテーマに描いたイラストをパッケージに採用した。そこには四世代が代々紡いできた歴史と想いが詰まっている、自給自足の原点の味わいを表現している。
「田んぼが元気になれば、少しずつ環境が良くなり、その土地の川の水も山も、微生物や動物の命にもつながっていく。私たちのような蔵の酒を飲んでもらうことで、日本の農業を守ることにつながるということを知ってもらえたら。この機会に「農!と言える酒蔵の会」に参加している蔵の活動を知っていただき、ぜひファンになってもらえたらうれしい」と仁井田氏。
農家の視点が原点。関西屈指の農醸一貫蔵がつくる酒|秋鹿酒造

精米から始まり、麹、酒母、醪(もろみ)すべての工程において貴重な原料米を一粒たりとも無駄にしない、できるだけ多くの酒を醸造するというポリシーに立って製造を行っている。醪の最後の搾りでは、ぎゅーっと最後の一滴まで絞り切り、米を最後まで活かし、使い切ることを造りのモットーとしている。
全国にはさまざまな歴史を持った蔵があるが、元々酒蔵だった蔵もあれば、農家から酒蔵になった蔵もある。大阪府能勢町にある秋鹿酒造は、米農家から歴史をスタートした蔵だ。秋鹿酒造の酒づくりはまさに「農醸一貫」。創業者の代から引き継ぐ田んぼで、1980年より山田錦を自社栽培している。
幼い頃から農薬を使う慣行栽培を見てきた現蔵元の奥裕明氏。人間の健康や土壌に影響を与える農薬を使う栽培は、「自分の代では経験したくない」という想いから徐々に農薬や化学・有機肥料の使用量を減らし、現在は完全無農薬で酒米栽培を行なっている。酒づくりの過程で生まれる酒粕やもみ殻、米ぬかなどの副産物を肥料として使用する工夫も。自ら取り組む農業と醸造が一体となる、循環を大切にした酒づくりを行なっている。
「米づくりの段階で、酒づくりの7〜8割は終わっていると思っています。洗米などの原料処理よりも前の米づくりから、酒の味は決まっているんですよね。僕たち「農!と言える酒蔵の会」のメンバーはみんなそういう思いで酒をつくっている。でなければ、やっている意味がない」と語ってくれた。
118人の農家から引き継ぐ想いと伝統がつまった酒|関谷醸造

関谷醸造の「蓬莱泉 純米大吟醸 摩訶® まか」。全量自社栽培の「夢山水」を使用したやわらかい口当たりとすっきりした飲みごこちの酒。創業150周年の節目に生まれた数量限定の希少な銘柄だ。
愛知県北部標高450mの自然豊かな山間部で酒を醸す蔵、関谷醸造。周辺農家の高齢化にともない生じる相次ぐ離農をきっかけに、地元に点在する合計40ha(東京ドームおよそ8.5個分)の田んぼで、米づくりから酒づくりを行なっている。
地域で一番米を使う事業者である自分たちがこの問題に責任を持ちたい、と蔵周辺13km圏内に点在する300枚近い手付かずの田んぼを、118人の地主から引き継いだ蔵元の関谷健氏。こうして醸される酒には、先人からの技術と、奥三河の土壌を育んできた農家から受け継ぐ想いと恵みが詰まっている。
酒づくり以外にも地酒のおいしさを知ってもらうための活動も欠かさない。近年では名古屋市内に日本酒バーをオープン、そのほかにも酒のオーダメイド、酒造り体験施設を運営するなど、日本酒の奥深さと楽しさを一般向けに知ってもらうための努力を惜しまない。多くの人に日本酒に触れてもらうことで、多方面へ向けて未来へのバトンをつないでいく。
「私たちがつくる酒から生まれる雰囲気や空気に触れていただき、まずはおいしさを知ってもらいたい。こういったイベントを機に酒や蔵に興味を持ってもらい、もっと知りたい、実際に訪れたいと思ってもらえるきっかけになれば」と関谷氏。
これまでの30年、これからの30年をつむぐ「真の地酒」|西岡本店

「私たちの酒づくりは“いま”の売り上げだけを見るのではなく、ずっとこれからも続いていく米、酒づくりの活動をどうやって続けていくかがテーマ」と語ってくれた西岡氏。
関東の名峰「筑波山」の麓で1782年より酒づくりを行う西岡本店。かつては、普通酒(吟醸酒・純米酒・本醸造酒など特定名称酒として区分されない日本酒)をメインに製造していたが、2011年より全量地元産米で醸す純米酒醸造に取り組んでいる蔵だ。
東京で商社マンを経験し家業を継いだ、八代目蔵元で杜氏の西岡勇一郎氏。地元に戻ってきた時「酒の出荷量が伸び悩んでいるこの時代、いままで通りのことをやっても家業を守り抜くことはできない。一代平均30年といわれる酒蔵事業で先代が築いてきた蔵を引き継ぎ、自分はこの地でこれから30年何をしていったらいいのだろう」という疑問が沸いたという。
改めて自分自身がどんな酒だったら魅力を感じるのだろうと考えたとき、思い描いたのは「真の地酒」だった。「ほかの地を訪れたときに自分が飲んでみたい、買いたいのはやはり“その土地のもの”がいい。裏面を見た時に、他県の工場で製造・加工されていたり、原料が違う土地のものではがっかりすることがある。だったら自分たちも他県から取り寄せた米で酒を醸すのではなく、原料の栽培から製造まで地元でおこなう真の地酒をつくりたいと思ったんです」。こうして全量地元産米を使用した、米の味を最大限に引き出す純米酒製造へと切り替えていった。徐々に自社栽培米の比率を上げながらも、契約農家以外に地元高校農業科との産学連携で栽培した米を使用するなど「この地」でしかできない取り組みも行う。
胸を張って「地元の酒です」と言えることが嬉しいと語る西岡氏。「花の井」を手に会場で筑波の自然へと想いを馳せて味わってみてほしい。
応援したい蔵を見つけて、味わいながら話を聞く都会で味わう贅沢で豊かな酒時間

農!と言える酒蔵の会のメンバー同士、会場でも和気藹々としているのが印象的だった。同じ志を持つ蔵同士、情報交換もよく行い日頃から仲がいいという。左から、関谷健氏(関谷醸造)、西岡勇一郎氏(西岡本店)、奥裕明氏(秋鹿酒造)、仁井田穏彦氏(仁井田本家)。
ホームページやパッケージだけではわからない、それぞれの蔵が伝えたい温度のある話を聞いた1日だった。それはスーパーマーケットでも、ほかの酒蔵のイベントでも叶わない贅沢な時間だったように思う。
酒蔵は「酒づくり」をしているのではなく、それぞれの地域の景色と文化を守り継承するために米をつくり、酒を醸し、人を育てている。日本酒文化はもちろん、故郷の里山の風景を守りたいと願う蔵元たちの言葉には、「循環」を感じるサステナビリティへのヒントが詰まっていたように思う。私たちが酒を呑むことで、田んぼ、農業が守られ、水、微生物、森、山、海へとつながっていることに改めて気付かされる機会になった。
とはいえ、まずは難しいことを考えずに純粋にそのグラスに注がれた一杯を味わってほしい。どの蔵元も「まずはおいしいと感じてほしい。それから酒を、蔵を知ってファンになってくれたらうれしい」と話していたのが印象的だった。何よりも「おいしい、楽しい」と感じ、ひとつひとつ知っていくことが、これからの未来へ“続いていく”ことの一端を担うのを誰よりも知っているのは、私たち消費者なのかもしれない。新たな蔵との出会い、そして酒から生まれる豊かさに触れられたイベントだった。

松浦 裕香里 (サステナブルフードスペシャリスト)東京出身。環境と循環を考えるフーディー。有機食品メーカー広報を経験し2018年に独立。サステナブルフードのスペシャリストとして、持続可能な食に精通したその確かな知識と情報もとに、執筆、PRマーケティング、レシピ開発など幅広く活動中。2021年より始めた取材で訪れた酒蔵の数は30以上。
https://www.instagram.com/yukari_matsuura_/
Latest Articles
ELEMINIST Recommends
