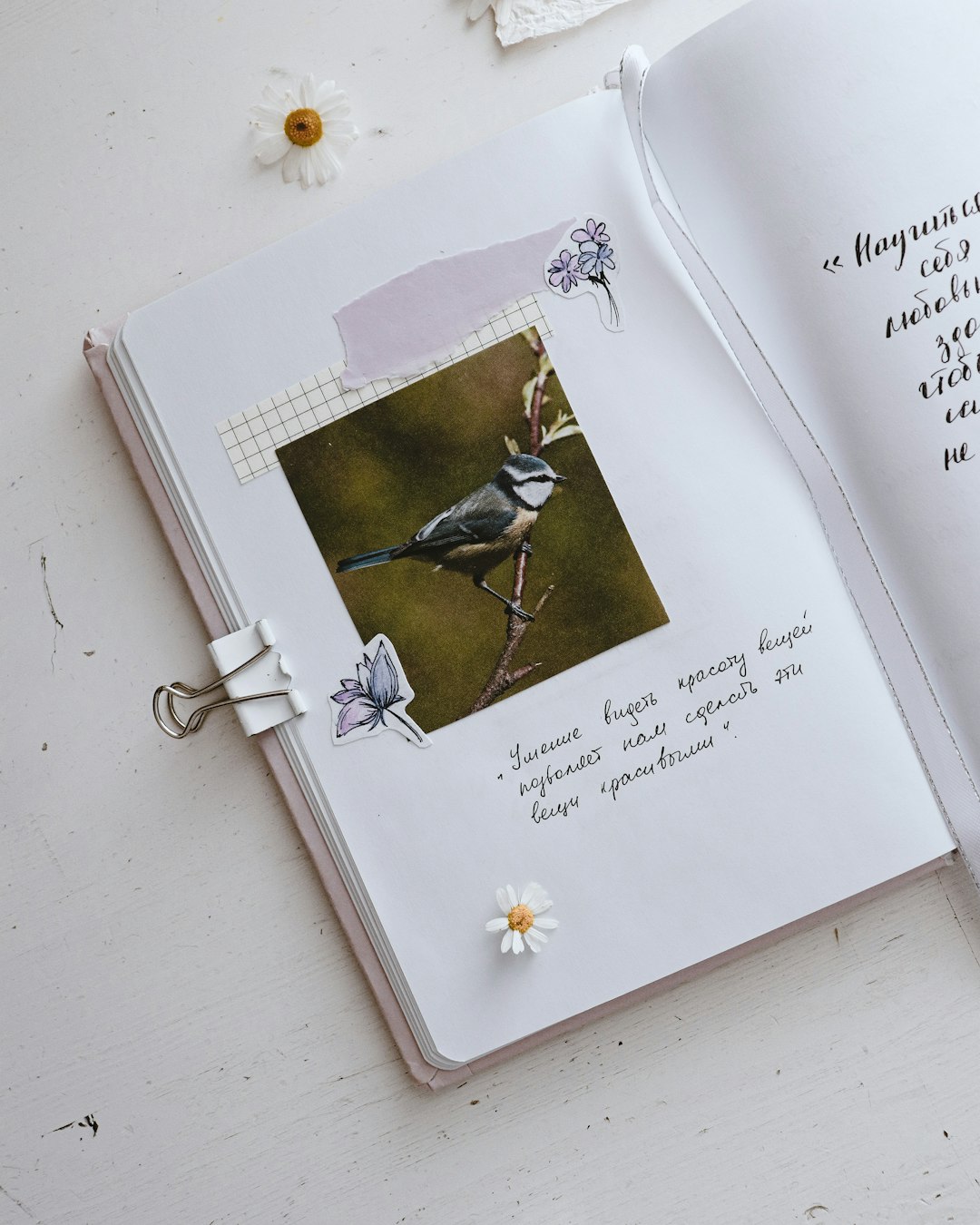サステナブルな暮らしとは いますぐできる15の具体例

Photo by Svitlana on Unsplash
美しい地球を未来へつないでいくために、サステナブルな暮らしが求められている。サステナブルな暮らしと聞くと難しく感じられるかもしれないが、日常のなかの少しのアクションで手軽にはじめられるものだ。本記事では、サステナブルな暮らしのための15の具体例を紹介する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
サステナブルとは

Photo by Brian Garrity on Unsplash
サステナブルは「sustain(持続する)」と「able(可能な)」からなる言葉で、「持続可能な」という意味を持つ。サステナブルは未来について考える際のキーワードであり、地球上の資源を次世代へつなぐための配慮や行動を指して使われる。
環境・社会・経済の持続可能性を示す概念としても用いられるサステナブルは、2015年に国連で採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」と関わりの深い言葉である。現在、世界全体でSDGsを推進し、サステナブルな社会の実現を目指している。私たちが、いまある地球環境や社会を維持し、将来世代に豊かな形で託すためには、サステナブルな社会の実現が必要なのだ。
エコやエシカルとの違い
エコは「生態学」を意味し、エコロジーの略である。地球環境にやさしいという意味合いで使われることが多い。
エコとサステナブルは意味合いの近い言葉ではあるが、サステナブルは地球環境にとどまらず包括的な意味を持つ。持続可能な開発には、経済成長、社会的包摂、環境保護の3つの核となる要素の調和が欠かせないとされている。(※1)サステナブルという言葉には複数の要素が絡んでいることを覚えておこう。
一方で、エシカルは直訳すると「倫理的な」という意味である。2015年に設立された「一般社団法人エシカル協会」は、エシカルを「人や地球環境、社会、地域に配慮した考え方や行動」と定義している。(※2)
サステナブルな暮らしとは

Photo by Superkitina on Unsplash
サステナブルな暮らしとは、意味通りだと持続可能な暮らし。持続可能な開発目標であるSDGsが自然環境や社会、経済に配慮した内容であるように、サステナブルな暮らしも地球全体のさまざまなことに配慮した暮らしである。平たくいうと、いまある地球の状態を少しでもいい状態で次世代につなぐための、未来に配慮した暮らしのことだ。
サステナブルな暮らしには、エコの要素とエシカルな視点が欠かせない。環境にやさしいエコなアイテムを日常生活に取り入れることは、サステナブルな暮らしのひとつの方法である。また、エシカルな考え方にもとづくエシカル消費もサステナブルな暮らしといえるだろう。エシカルな考え方や行動があってこそ、サステナブルな社会を実現できるのだ。
サステナブルな暮らしが求められる背景

Photo by Joe Yates on Unsplash
「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に公表した報告書のなかで、持続可能な開発は「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」と表現されている。(※3)
しかし、現在の地球では気候変動や生物多様性の損失といった環境問題や、貧困や教育格差をはじめとする社会課題が深刻だ。いまのままでは、この先豊かな生活を続けていくことは難しく、将来世代が生きていく未来に負の遺産を残してしまう。
地球への負荷を減らし、よりよい未来にするためには、SDGsを指針にしたアクションが必要であり、現に、世界規模で推進されている。そして、アクションには私たち一人ひとりが個人でできることが多数ある。
これからの地球のための行動を生活に取り入れるのが、サステナブルな暮らしである。地球の自然や資源を守り、これからも豊かに暮らしていくためにはサステナブルな暮らしの実践が必要だ。
サステナブルな暮らしの具体例
日常生活のなかには、サステナブルな暮らしにつながるポイントがたくさんある。以下では、ファッションや食事、買い物など身近な分野に潜む15のアクションを紹介しよう。
1. マイボトルを持ち歩く
マイボトルを持ち歩くと、ごみを減らすことができる。外出先で飲み物を買うと、ペットボトルや使い捨てカップなどは一度きりしか使われずに廃棄の対象に。マイボトルには、環境問題に貢献できたり、飲み物代が節約できたりというメリットがたくさんある。近年は、マイボトル持参で飲料代が割引になるお店も増えているので、積極的に活用しよう。
2. マイバッグを活用する

Photo by Benjamin Brunner on Unsplash
レジ袋有料化にともない、マイバッグを持ち歩く人が増えただろう。マイバッグはプラスチックごみを減らし、資源の無駄使いやマイクロプラスチック問題とも深くつながっている。買い物には必ずマイバッグを持参したい。
3. ものを長く使う
ものをすぐに捨てることは、大量生産・大量消費・大量廃棄の流れを助長する。ごみが増えれば増えるほど環境に負荷をかけるので、ものを大事に長く使うことこそ、サステナブルな暮らしの基本なのだ。ものが壊れたら修理を試みたり、ほかの使い道がないか考えてみたりというのも、あわせて行いたい。
4. 不用品をリサイクルする
リサイクルできるものは、ごみに捨てるのではなくリサイクルに出すようにしよう。ごみをしっかり分別し、自治体が定める方法で出す。そんな基本的なことも、サステナブルな暮らしのためのアクションだ。
5. 着なくなった服をリメイクする

Photo by tata toto on Unsplash
流行が過ぎた服やサイズが合わなくなった服は、すぐに廃棄するのではなくリメイクを検討しよう。ちょっとした工夫を加えることで、また着られるようになったり違うアイテムに生まれ変わったりする。自分でリメイクすると愛着が湧き、より大事にできるかもしれない。
6. フリマアプリを活用する
不用品は、処分する前にフリマアプリに出品してみてはいかがだろうか。一見不用品でも、必要としている人が引き継いで大事に使ってくれるかもしれない。サイズアウトした子ども服は、おさがりとして着てくれる人に譲るのもいい。
7. 環境や人に配慮した商品を選ぶ
買い物は投票といわれる時代、商品を選ぶときには環境や人へのやさしさも考慮したい。ブランドの方針をチェックして、応援したい企業の商品を選ぶのもいいだろう。ほかにも、働く人の労働環境や地球環境へ配慮したフェアトレードや、各種認証などを基準にするのも方法のひとつ。プラスチックフリーでつくられているものや循環型素材が採用されているもの、オーガニック製品など、素材で選ぶのもポイントだ。
8. 食事を残さず食べる
食事を残さず食べて、食品ロスを削減しよう。農林水産省および環境省の公表によると、まだ食べられるのに捨てられている食品ロスの量は年間522万トン。(※4)国民一人当たりに換算すると、毎日お茶碗一杯分の食べ物が捨てられている計算だ。「残さず食べる」という私たち一人ひとりの心がけで食品ロスは確実に減らせることを覚えておきたい。
9. 賞味期限の近いものを選ぶ
賞味期限の近いものを選んで買うことは、食品ロスの削減につながっている。消費者庁をはじめとする各省庁が消費者に呼びかけている「てまえどり」は、陳列棚の手前に並んでいる期限が近いものから選ぶという購買行動であり、食品ロス削減のための取り組みのひとつだ。すぐに食べる食品に関しては、積極的にてまえどりを実践したい。
10. 地産地消を意識する

Photo by Dan Gold on Unsplash
地産地消が行われると、食材の運搬の際にエネルギーを消費せずに済み、ガスの発生を抑えられる。ほかにも、消費者は新鮮な食材を安く購入できるメリットがある。地域で採れた食材を食べることで、地域の食文化への理解も深まるだろう。
11. コンポストを活用する
コンポストとは、微生物の働きによって生ごみを堆肥化する容器のこと。コンポストを活用するとごみの量が減るため、ごみ袋代の節約になるし、焼却の際のCO2の排出量を削減できる。有機物由来の堆肥は、家庭菜園や花の栽培に安心して使うことができる点もメリットだ。近年は、集合住宅のベランダや室内でも使いやすい都市型コンポストも普及している。
12. エネルギー・資源を大切に使う
資源は有限であり、使用時にエネルギーを必要とすることを頭に入れて、こまめに節水・節電するように心がけよう。「使わない部屋の電気を消す」「水の出し過ぎに注意する」など、同居人を巻き込んで行うのが重要だ。
13. 再生可能エネルギーを利用する

Photo by Nicholas Doherty on Unsplash
暮らしに欠かせない電気やガスは、石油や石炭などの有限な資源と引き換えにつくられている。また、火力発電で発生する温室効果ガスは気候変動問題に大きく関わっており、環境負荷がかかっている。
昨今は太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーを電源とするプランを設けている電気事業者も増えている。再生可能エネルギーはCO2の排出量が実質0であり、環境負荷が低い。特別な設備を用意せずに、契約を切り替えるだけで利用できるので、積極的に検討してみよう。(※5)
14. 無駄をなくしてシンプルに暮らす
シンプルに暮らすことは、サステナブルな暮らしそのものかもしれない。ものが少ないと整理整頓できる分、足りないものが一目瞭然。必要なものを必要な分だけ購入できて、無駄が減る。さらに、所持品に目が行き届くため、メンテナンスにも時間をかけられて、結果的にものを長く使うことができるだろう。「ミニマリスト」となるとハードルが高いかもしれないが、身の回りのものを整理する機会を設けてみよう。
15. パブリックコメントに参加する
サステナブルな社会の実現のためには、より多くの人の声が政策に反映されることが望ましい。パブリックコメントとは、行政がルールを制定するときに一般から意見を募集する仕組みであり、国民が政府に声を届ける機会のひとつである。日本では2013年から2014年にかけて、新しい「エネルギー基本計画」策定においてパブリックコメントが適用され、国民の意見が政府原案にプラスされた例がある。(※6)
できることからサステナブルな暮らしを実践しよう
サステナブルな暮らしには明確な答えがあるわけではないし、正解もない。ただ、個人の小さなアクションが、未来を少しずつ着実にいい方向に変えるということを覚えておきたい。
これまでの生活を一気に変えようとすると難しい。最初から完璧を目指す必要はないので、ライフスタイルに合った方法で、自分らしくサステナブルライフをはじめよう。
※1 SDGs ― よくある質問 |国際連合広報センター
※2 エシカル とは?| 一般社団法人エシカル協会
※3 持続可能な開発|外務省
※4 食品ロスについて知る・学ぶ|消費者庁
※5 「再エネ スタート」はじめてみませんか 再エネ活用|環境省
※6 新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた パブリックコメントの結果について P1〜2|資源エネルギー庁
Read More
Latest Articles
ELEMINIST Recommends